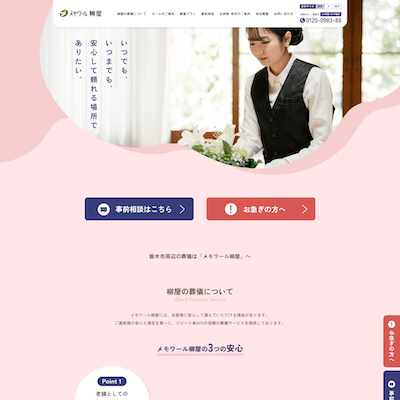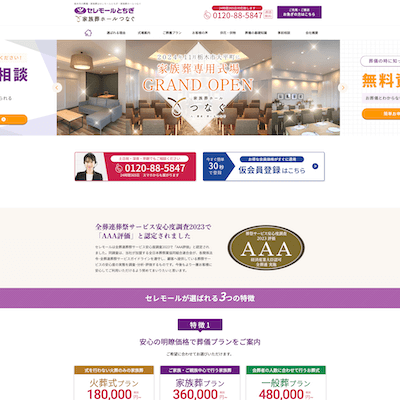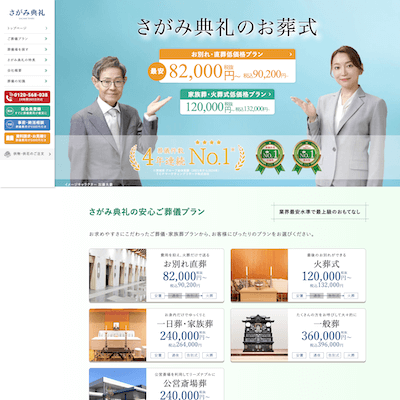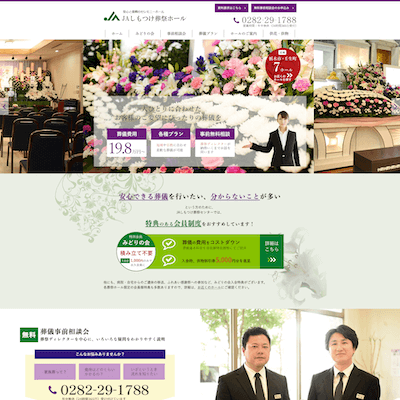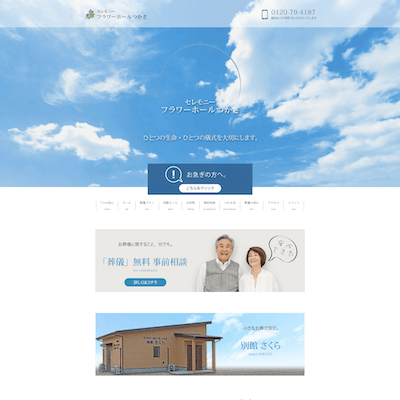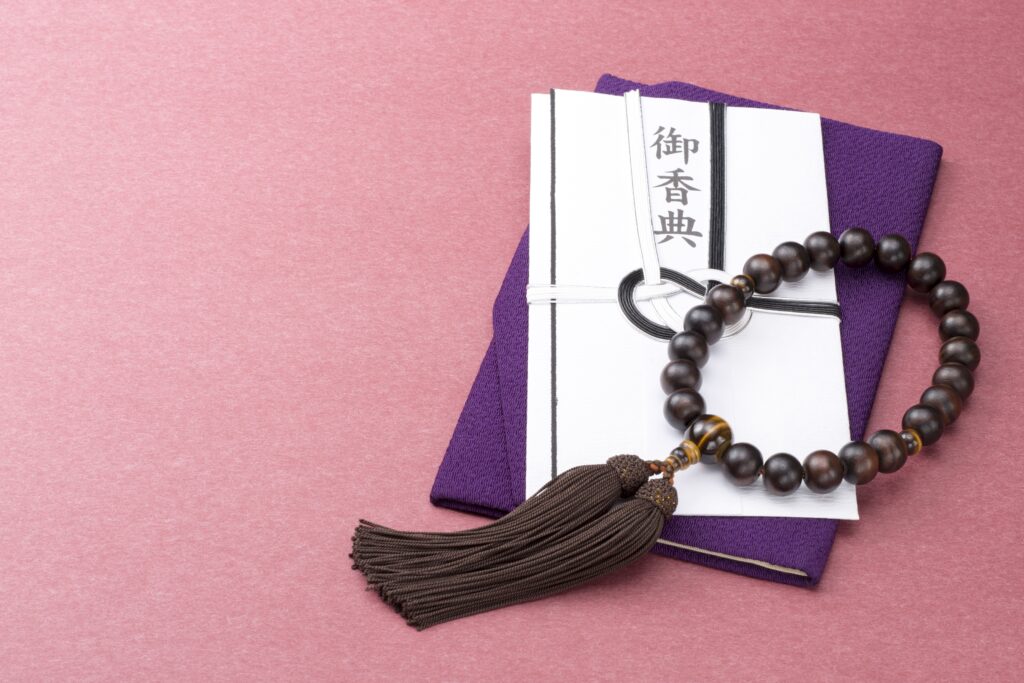神道の儀式は、長い歴史の中で仏教の影響を受けながらも、根本的な考え方には大きな違いがあります。そのため、葬儀の形式や参列時のマナーにも特徴的な違いが存在します。この記事では、神式葬儀の概要や、参列時に知っておきたいマナーと注意点をくわしく解説しますので、参考にしてください。
神式葬儀「神葬祭」とは?仏式との根本的な違い
神葬祭とは、神道の教えにもとづくお葬式のことを指します。仏教のものとは違い、独自の手順や意味合いがある儀式で、故人を祖先の神として祀ることを目的としています。仏教では、故人の魂を極楽浄土へ導くことを目的とした葬儀が行われますが、神道では、故人の魂を祖先の神霊として祀り、家の守り神となるよう祈る独自の儀式が行われます。
神葬祭の概要
神葬祭では、亡くなった方の魂が家族の守り神として永く見守る存在になることを願い、神々のもとへと送り出す儀式が行われます。また死は穢れとされているため、そこから生じる穢れを取り除くための清めの儀式が各段階で執り行われるのが特徴です。仏式との違い
神道の葬儀は神葬祭と呼ばれ、故人の死による穢れを清めるとともに、故人を自宅の祖霊舎で神として祀り守り神となるように祈ります。これに対し、仏式の葬儀では、故人を成仏させるための経典を上げるなどの供養を行うことがおもな目的です。神社では営まれない
仏式の葬儀は、自宅や斎場だけでなく、寺院にて営まれることも少なくありません。一方で神葬祭は、自宅や斎場を利用して行われます。神道において死は穢れと見なされるため、神社のような聖域での葬儀は行われません。神道の儀式を通じて、故人は神のひとりとして祀られ、神職や遺族よりも高い存在として敬われます。
神道式のお葬式の具体的な流れ
神道式のお葬式は、仏式とは違う流れで進められます。参列する際や遺族として対応する際には、基本的な流れを知っておくことが大切です。神道式のお葬式の具体的な流れを、時系列で分かりやすく紹介しますので、参考にしてください。帰幽奉告
家族の死を、自宅の祖霊舎に伝える儀式として、帰幽奉告が行われます。祖霊舎に死の穢れが入らないようにするために、扉を閉めて白い紙を貼る儀式も同時に行われます。この封は忌明けまで続け、普段のお供えや拝礼もお休みし故人への祀りを優先するのが一般的です。通夜祭
通夜式は、仏式の通夜にあたる儀式です。神職が祝詞を唱え、参列者がひとりずつ榊の枝を供えます。通夜祭は、故人の魂を慰め、神のもとへ無事に導くための大切な儀式です。葬場祭
葬場祭では、手水の儀や修祓の儀でお清めを行います。仏式の葬儀や告別式で行われる弔辞の読み上げや祝詞の奉納のように、神式でも厳かな儀式があります。仏教では焼香をするのに対し、神道では玉串を奉げます。火葬祭
葬場祭のあと、火葬場で行うのが火葬祭です。神道では魂を敬い清らかに送り出すという考えが重視されます。五十日を過ぎた頃を目安に埋葬する風習があり、お墓に納骨する際には埋葬祭を行います。帰家祭
すべての葬儀が終わったあと、喪家は自宅で塩や手水を使って身を清めます。祓いの儀式を終えたら、葬儀を担当した神職や世話役への感謝を込めて直会という宴を開きます。神棚の封は、納骨が済んだあとの没日から約50日目に開くのが一般的です。神式葬儀に参列するときのマナーと注意点
神式の葬儀は仏式とは異なる独特の作法や信念にもとづいて執り行われるため、参列時にはあらかじめマナーや注意点を理解しておくことが重要です。ここからは、神式ならではの参列時のマナーや、仏式との違いについて分かりやすく紹介します。玉串奉奠の作法
神式の葬儀でお参りする際は、はじめに神職へ一礼し、続いて神前に一礼します。その後、玉串を供えてから、拝礼を行います。拝礼は、神社で参拝する際と同様に、二礼、二拍手、一礼です。ただし慶事であるため、中間の二拍手は音を鳴らさない忍び手で行わなくてはいけません。神葬祭にふさわしい不祝儀袋の選び方
神葬祭の不祝儀袋は、一般的な仏式の葬式で選ばれるものと同じですが、表書きは御玉串料・御榊料・御霊前のいずれかを記す必要があります。香典は、香を供えることで故人をしのぶ仏教の言葉であるため、神式では御香典とは書きません。また蓮の花は仏教を象徴する絵柄のため、表書きや袋などに使用しないように注意が必要です。神式で包む金額の目安に関しては、仏式と同程度で問題ありません。