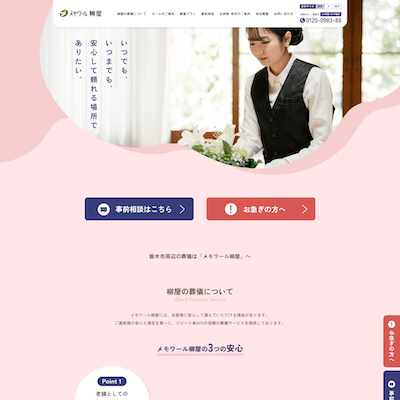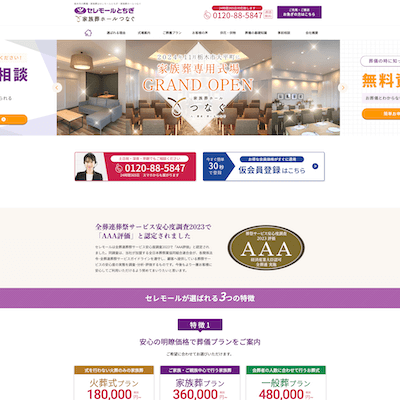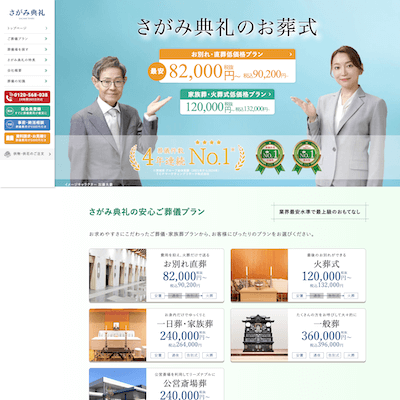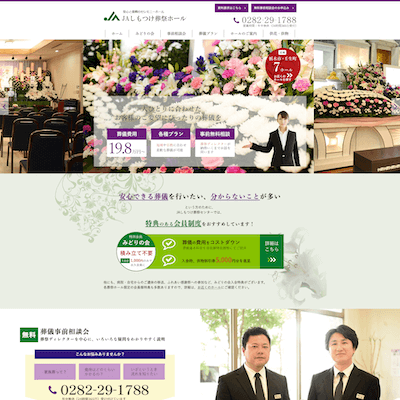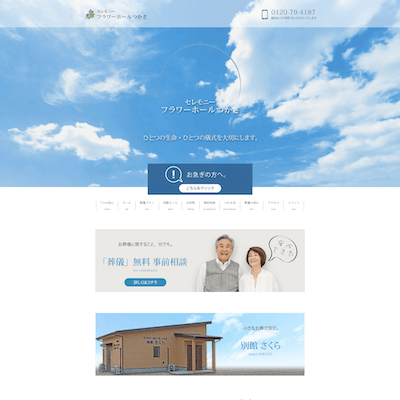多くの自治体では、国民健康保険に加入している方が死亡したときに申請することで葬祭費が支給されます。とはいえ、その詳細を知らないという方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、栃木県の葬祭支給額や申請方法、申請期限などについて解説します。この記事を読んで、スムーズな葬祭費の受け取りに役立ててください。
葬祭費とは?栃木市で受け取れる金額と基本ポイント
栃木市では、条件を満たして申請することで一定額の葬祭費が支給されます。ここでは、葬祭費の概要や栃木市における支給額、対象者や注意点について解説します。葬祭費の概要
葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなった際に、葬儀費用の一部を補助するために支給される給付金のことです。葬祭費用の目的は、亡くなった方の葬儀にともなう経済的負担を軽減し、誰もがスムーズに葬儀をおこなえるようサポートすることとされています。申請対象者は、喪主などの葬儀をおこなった者とされており、葬儀が終わった日の翌日から2年以内に申請できるようになっています。
栃木市の支給額
栃木市では、葬祭費として一律5万円が支給されます。ただし、他の社会保険から葬祭費に充当できるものを受取れる場合や、交通事故や事件などが原因で、第三者から葬祭費に充当できる賠償金を受取れる場合には支給されないため注意が必要です。この金額は他の自治体と比較しても標準的ですが、葬儀の内容が「火葬のみ」の場合には支給されない自治体もあります。
対象者と条件
葬祭費の受給対象者は、遺族など葬儀を主催した方です。受給の条件は、国民健康保険もしくは75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際、その葬儀をおこなった場合とされています。ただし、申請は葬儀の翌日から2年以内におこなわないと、申請する権利を失ってしまうため注意が必要です。また、申請先は葬祭費を受取る喪主が居住する自治体ではなく、亡くなった方の住民票があった自治体になります。
葬祭費の申請方法と必要書類まとめ
葬祭費の受給を申請する際には、事前に必要書類や手続きの流れを把握しておくことが重要です。ここでは、申請窓口や必要書類、注意点について解説します。申請窓口と受付時間
葬祭費の申請は、栃木市役所の保険年金課または各総合支所(大平・藤岡・都賀・西方・岩舟)で受けつけています。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。タイミングによっては窓口が混雑している場合もあるため、事前に電話で問い合わせるとスムーズに申請できるでしょう。また、郵送での申請も受けつけており、さまざまな事情により役所に出向くのが難しい場合は、詳細を問い合わせたうえ郵送で申請するのもおすすめです。
必要書類まとめ
葬祭費の申請には、葬祭費請求書(窓口で入手または市のウェブサイトからダウンロード)、身分証明書の写し(運転免許証やマイナンバーカード)、亡くなった方の国民健康保険証、名入りされた会葬礼状や領収証など施主をチェックできるもの、通帳など口座情報のわかるものといった書類が必要です。申請時の注意点
葬祭費の請求期限は、葬儀の翌日から2年以内とされています。書類に記載ミスや不備があると再提出となるため、申請は余裕を持っておこないましょう。また、葬祭費の支給は、申請を受けつけた日から1~2ヵ月後に振込によっておこなわれます。さらに、提出した書類は返却されないため、必要書類を事前にコピーしておくのがよいでしょう。
葬祭費申請の期限と注意点
葬祭費は期限までに申請しないと受給できなくなってしまいます。また、事前に手続きの注意点を把握しておくことも重要です。ここでは、申請期限や注意すべきポイントについて解説します。申請期限について
栃木市における葬祭費の申請期限は葬儀の翌日から2年以内とされています。この期間を過ぎると、いかなる理由があっても支給されません。例えば、2025年7月10日に葬儀をおこなった場合、2027年7月10日が申請期限となります。万が一書類に不備や不足があった場合、申請が期限に間に合わないことも想定されるため、早めの申請が推奨されます。
申請先の自治体
葬祭費受給の申請は栃木市役所保険年金課または各総合支所(大平・藤岡・都賀・西方・岩舟)で受けつけています。申請前に電話や窓口で必要書類や手続きの詳細を問い合わせするとスムーズに手続きできるでしょう。また、事前に必要書類を準備し「栃木市役所保険年金課国保係」宛に郵送することで申請することも可能となっています。
申請前に把握しておくべきポイント
申請前には、被保険者が国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上の場合)に加入していたかどうかをチェックしましょう。また、亡くなった方が従前の社会保険に1年以上加入しており、その資格を失ってから3ヵ月以内である場合には、葬祭費は従前に加入していた社会保険から支給されるため注意が必要です。
さらに、申請期限の2年を過ぎないよう、早めに手続きを進める必要があります。総じて、書類不備や期限超過による不受理を防ぐため、申請書類の準備と提出は計画的におこないましょう。