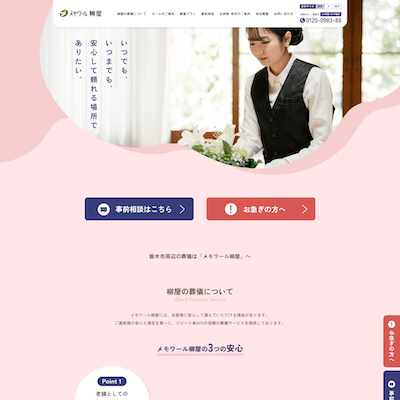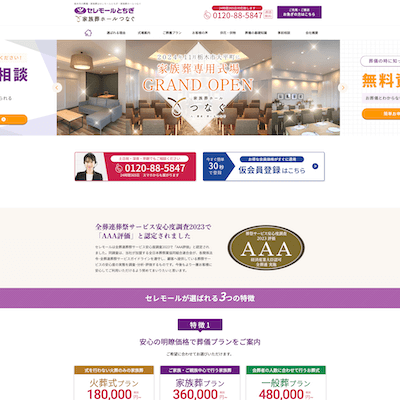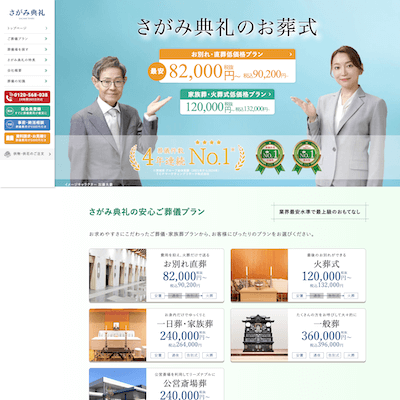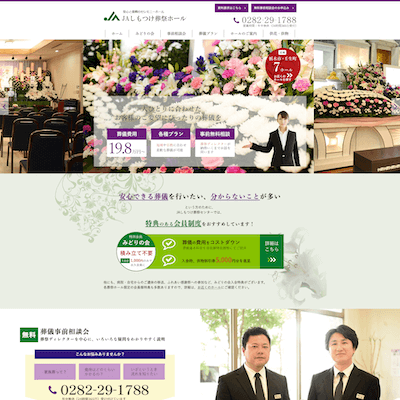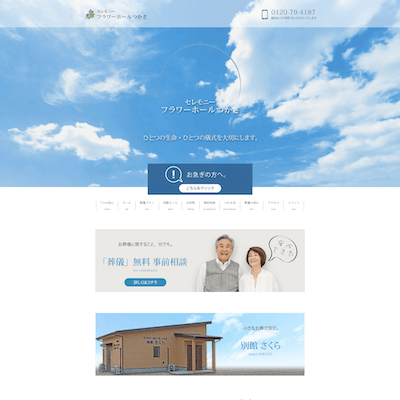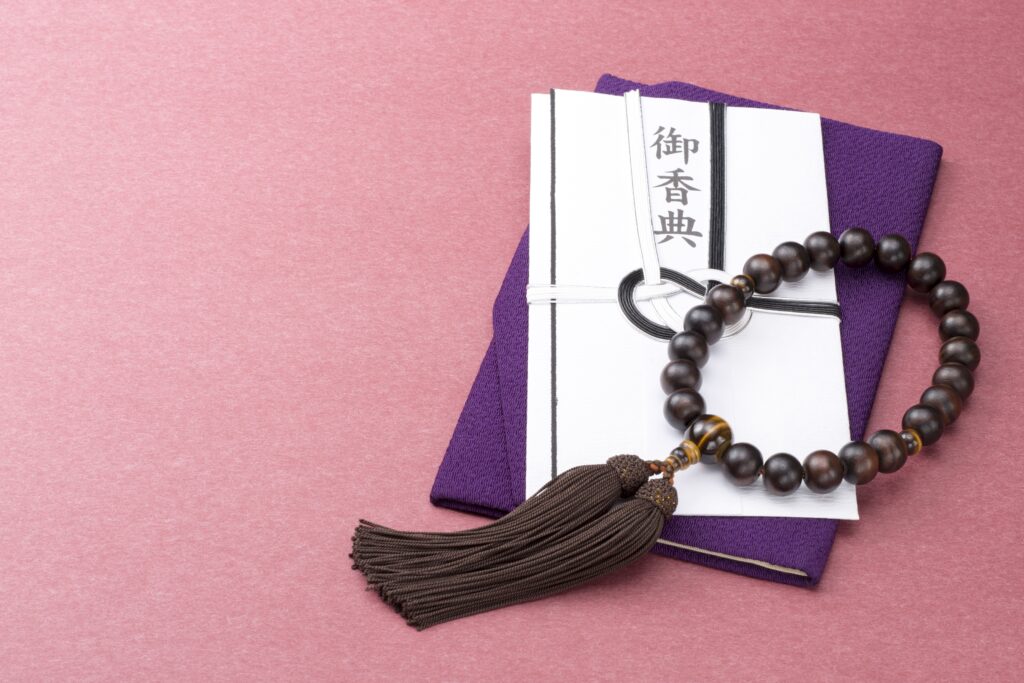葬儀には地域特有の風習やマナーが存在し、栃木県も例外ではありません。それらを知らずに栃木県で葬儀に参列してしまうと、勝手が分からず戸惑う場面も多いことでしょう。そこでこの記事では、栃木県における葬儀の風習やマナー、しきたりについて解説します。栃木県で葬儀に参列するご予定のある方は、この記事をぜひ参考になさってください。
栃木県に残る独特な葬儀風習とは?
栃木県は地域コミュニティの絆が強く、葬儀にもその精神が反映されています。伝統的な葬儀の儀式は、栃木の文化を象徴するものです。ここでは、栃木県に残る独特な葬儀風習を紹介します。三十五日法要を葬儀当日に行う風習
一般的に三十五日法要は、故人が亡くなられてから三十五日目に行う法要で、親族が集まり、読経や会食を行うのが基本です。しかし、栃木県の一部(特に栃木市周辺)では、葬儀当日に繰り上げ法要として、三十五日法要までを併せて行う風習があります。葬儀当日に行う場合は、菩提寺への事前確認や、香典・引き物の準備が必要となります。地域独自の風習があるため、親族として参列する際は、事前に施主や葬儀社へ確認しておくと安心です。
また、栃木市では葬儀用と三十五日用の香典を二つ用意するケースもあります。その際は「表書き」に注意が必要です。受付に出すのは葬儀用の香典で、「御霊前」とします。
一方、三十五日用の香典は、御霊前の袋の右上に「三十五日」と記載して準備するのが通例です。三十五日用の香典は受付には出さず、火葬場から戻ってから渡します(渡す場所やタイミングについては、葬儀社のスタッフに確認するとよいでしょう)。
栃木ならではの風習を理解し、故人を温かく送り出しましょう。
組内(くみうち)による助け合い
栃木県、とくに宇都宮市や栃木市といった地域コミュニティが強いエリアでは「組内(くみうち)」と呼ばれる自治会組織が葬儀一式を取り仕切っています。かつて土葬が主流だった時代、棺を運んだり墓を掘ったりする作業に多くの人手が必要だったため、近隣住民で助け合う文化が生まれました。現在では葬儀のほとんどを葬儀社が担う一方で、受付や会計、料理の手配などについては組内が担い、通夜振る舞いや精進落としで感謝を伝えるのが慣例となっています。
出棺時の「仮門(かりもん)」
栃木県に残る風習のひとつに、出棺時に「仮門(かりもん)」と呼ばれる簡易的な門を通る儀式があります。仮門の儀式は、故人が家から旅立つ際に、家族や近隣住民が作る竹でできた門で、故人の魂が迷わずあの世へ向かうことを願うものです。仮門をくぐる際に参列者が見送る姿は、伝統を重んじながら故人との別れを厳かに演出します。
花籠ふり(はなかごふり)で見送り
「花籠ふり(はなかごふり)」は、栃木県で特徴的な出棺の儀式です。参列者が細かくした紙を目の粗い籠に入れ、そこに竹の竿を取り付けたものをもちます。出棺の際に籠を振り、棺に紙片を振りかけることで、籠から紙が舞い落ちる様が花のように見えることにより、故人の冥福を祈り、魂を清らかに送り出す意味をもたせます。
花籠ふりは栃木県の農村部や地域コミュニティが強いエリアでよく見られ、参列者全員で故人を偲ぶ風習として根づいているのが特徴です。
枕返し
栃木県には、故人を安置する際に一度頭を南に向けてから北枕に戻すという独特の作法が、現代まで受け継がれています。一般的に北枕はお釈迦様の入滅時の姿勢にならうしきたりですが、栃木県ではこの“南に向ける”動作が「枕返し」と深く結びついていると考えられてきました。いったいなぜ、このような風習が根付いたのでしょう?
その伝承が残るひとつが、栃木市の大中寺。実はここに、仏さまに足を向けて寝ると、翌朝には向きが入れ替わっていたという「枕返しの間」があるのです。
また、大田原市の大雄寺にも「枕返しの幽霊」と呼ばれる掛け軸が伝わっています。
時は江戸時代中期。この掛け軸が飾られた「牡丹の間」で寝泊まりをした行商人が眠りから覚めると、この絵の幽霊が目の前に現れて仰天し、気付くと布団が180度回転していたのだとか。本来枕元にあった荷物と掛け軸は、足下に変わっていたそうです。
こうした土地固有の伝承が、現在の葬儀習慣にも影響しているといわれています。
「新生活運動」や「前火葬」など栃木特有の葬儀スタイル
栃木県の葬儀文化では、地域の歴史や価値観にもとづく独特なスタイルが存在します。ここでは、栃木特有の葬儀スタイルを紹介します。「新生活運動」による葬儀の簡素化
栃木県足利市では、冠婚葬祭の簡素化運動を推進する「新生活運動」が葬儀文化に影響を与えています。新生活運動は、冠婚葬祭にかかる過剰な費用をおさえ、簡素で合理的な生活を推奨するものです。具体的な新生活運動には、香典袋にお返し辞退のラベルを貼る「香典返し辞退運動の推進」と、花輪を出さず香典袋に「御花輪代」として花輪代相当額を入れる「花輪代方式の推進」などがあります。
また、葬儀においても、華美な祭壇や過度な接待を控え、家族葬や直葬を選ぶ傾向が強まっていることも特徴的です。とくに、栃木県の都市部では、参列者を親族に限定し、簡潔な儀式を行うケースも増えています。
栃木県に残る「前火葬」
火葬においては、通夜・葬儀・告別式の後に行う「後火葬」が一般的ですが、栃木県の一部地域では、葬儀前に火葬を行う「前火葬」の風習が残っています。「前火葬」の風習は、神道の影響や地域の歴史的背景から生まれたとされ、死をけがれととらえる考え方に由来しています。都市部では「前火葬」の風習は減少傾向にありますが、伝統を重んじる地域では「前火葬」が選ばれることも珍しくありません。
香典返しの辞退とその背景
栃木県では、香典返しを辞退するケースも多く見られます。とくに「新生活運動」の影響を受けた地域では、香典返しの風習を簡略化し、500円程度のタオルやハンカチを参列者に配る簡易的な返礼が一般的です。また、90歳以上の高齢者で、長生きして天寿をまっとうされて亡くなった場合には、紅白のタオルを配る風習も残っています。これは、故人の長寿を祝い、参列者への感謝を軽やかに表現する地域独特の文化です。
栃木県ならではの葬儀後におけるマナーとしきたり
葬儀後のマナーやしきたりについても、コミュニティの絆や宗教的背景を反映する独特な特徴があります。ここでは、栃木県ならではの葬儀後におけるマナーとしきたりを紹介します。清めの塩とかつお節
栃木県の一部地域では、葬儀の参列者が帰宅して玄関に入る前に、清めの塩を体に振りかけるとともにかつお節を口にする風習があります。これは神道にもとづいており、かつお節は神道の神饌(神にお供えする食べ物)としての役割を果たすと考えられていることから、けがれを清める儀式として行われている風習です。
かつお節は製造工程で燻されますが、神道では「燻す」という行為が「邪気を払う」あるいは「浄化する」と考えられています。
十三仏念仏(じゅうさんぶつねんぶつ)
栃木県には、葬儀のあとに「十三仏念仏(じゅうさんぶつねんぶつ)」と呼ばれる念仏を唱える風習があります。十三仏念仏の風習は、長く大きな数珠を複数人でもち、その数珠を皆で回しながら念仏を唱えることで故人の冥福を祈り、その功徳を何倍にも増やすという考えにもとづいていたものです。
十三仏念仏は、鎌倉時代末期の京都で疫病が蔓延した際に、後醍醐天皇の命によって十三仏念仏を行ったことで疫病を鎮めた出来事がきっかけとなっています。
七日ざらしの風習
栃木県には、葬儀後に、故人が着ていた衣服を北向きに干し、水をかけ続けて1週間放置する「七日ざらし」という風習があります。七日ざらしを行う際のポイントは、1週間に渡り衣類に水をかけ続け、常に濡れた状態を保つことです。七日ざらしの風習には、故人が衣類に残した現世への思いを洗い流すという意味が込められています。