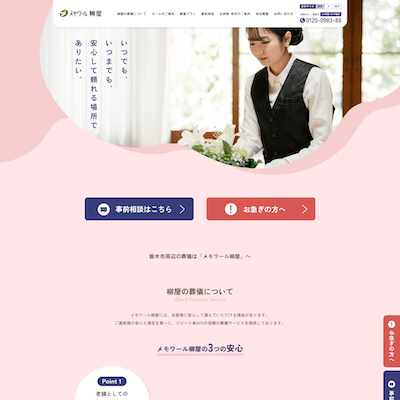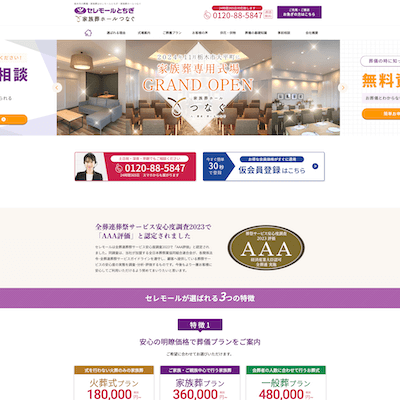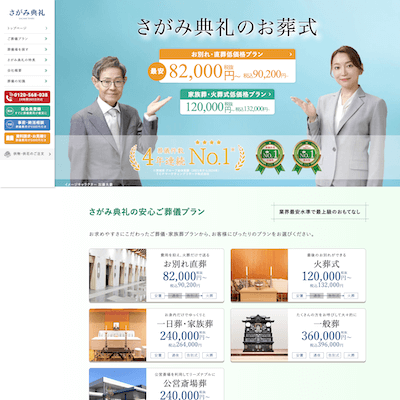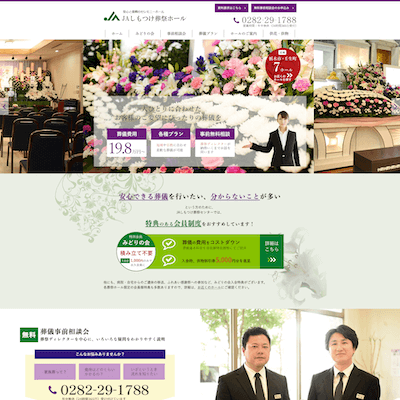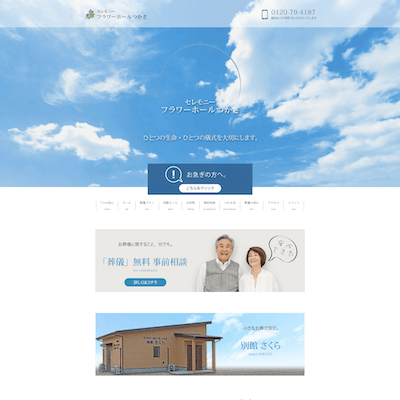葬儀の費用に関して不安に感じる方は多いでしょう。葬儀費用は地域性や風習によって差が出やすく、相場や内訳を知らないと費用が多くかかってしまうかもしれません。この記事では、葬儀費用の平均やプランごとの内訳、費用を抑えるためのポイントについて幅広く解説しているので参考にしてください。
葬儀費用の平均相場はいくら?
ここでは、2024年に発表された「第6回お葬式に関する全国調査(鎌倉新書)」のデータをもとに、葬儀費用の平均相場を解説します。葬儀費用の相場
全国の葬儀費用の平均額は約118.5万円です。ただし、地域によって2倍以上の差が生じるなど、大きな開きがあります。たとえば、東京都の葬儀費用は平均127.6万円で、全国平均よりも高い水準です。また、日本でもっとも高額な県は栃木県で、約179.5万円でした。一方で、もっとも安価な県は香川県で、約77.0万円です。このように、都道府県によって100万円近い差があるため、葬儀をどこで実施するかも大きなポイントです。
葬儀の形式別相場
もっとも費用に差が出るのが、葬儀の形式です。故人の家族や親族だけではなく、友人、知人、会社関係者、近所の方など、幅広い方が参列する一般層の相場は、161.3万円です。飲食代や返礼品の費用もかさむため、もっとも費用が高くなる傾向にあります。参列人数は変動しやすく、費用の見積もりを上回ることも少なくありません。また、家族・親族や親しい友人に限定して執り行う家族葬は、平均105.7万円です。一般葬よりも会場費・飲食費・返礼品費が少なくて済むため、費用を抑えられます。
一方、葬儀・告別式のみを1日で実施する一日葬の相場は、87.5万円です。加えて、通夜や告別式を実施せず、火葬だけ執り行う直葬の相場は、平均42.8万円です。直葬は参列者を招かず、身内だけで火葬場に集まるケースが多いため、費用を大幅に抑えられます。
葬儀費用の内訳と追加料金
葬儀費用は、葬儀を執り行う基本料金に加え、参列者への接待費用や宗教者への謝礼、さらには当日の対応やオプションによって追加される費用など、さまざまな要素で構成されています。葬儀費用の内訳
葬儀費用は大きく分けて、葬儀費用、参列者への接待費用、宗教者への費用の3つに分類されます。まず、葬儀費用とは、通夜から葬儀・告別式までのサービス代です。これには、セレモニーホールや斎場の使用料、祭壇・棺・遺影の準備、司会進行スタッフの人件費、寝台車や霊柩車の費用などが含まれます。しかし火葬料金については、葬儀社が一時的に立て替えるか、喪主が火葬場に直接支払う形となるのが一般的であるため、計画しておかなければ急な出費となる可能性があり、注意が必要です。
次に、接待費用として、通夜振る舞いや精進落としなどの飲食費用、香典返しなどの返礼品に関する費用がかかります。接待費用の概算については、見積もり段階で提示されますが、実際の参列者数により変動することが多いため、最終的な請求額と差が出ることを想定しておきましょう。
最後に、宗教者への費用は、僧侶による読経や戒名の授与などへの費用です。また、遠方から来場依頼する際には御車料や御膳料といった名目の謝礼が加わることもあります。御車料、御膳料とは、原則として喪主から直接宗教者へ渡すもので、葬儀社の見積もりには含まれていません。
さらに、お布施は感謝料の位置づけのため、各家庭や、故人と寺との関係により変化し、どのくらい必要かは明確に決められていません。金額がわからない場合は、直接確認するとよいでしょう。近年では菩提寺がない方も多いので、その場合には定額で宗教者を紹介するサービスを利用するのがおすすめです。
追加料金
葬儀社のプランには、基本サービスのみが含まれています。オプションを依頼することで、それ以外のサービスを追加できますが、追加費用が発生することがあります。たとえば、故人の体をていねいに洗い清める湯灌や、遺体の長期保存を目的としたエンバーミングなどは、基本プランには含まれておらず、別途費用が必要です。
また、棺や骨壺、祭壇装飾などをグレードアップした場合にも追加料金がかかります。さらに、参列者の人数が想定より増えた場合にも、飲食や返礼品の費用が追加で発生します。
葬式は、参列者の変更・追加などにより、急きょ料理を追加したり、香典返しを補充したりする必要があるため、とくに大規模な葬儀では費用の上乗せがめずらしくありません。とくに、葬儀は参列者を確定しづらく、予想外の出費はどうしても発生します。
したがって、出費できる金額ぎりぎりで葬儀を計画してしまうと、予算オーバーとなりやすいので注意しましょう。参列者の増加や、オプション追加が発生したら、その都度見積もりを取得し、金額を明確にすることをおすすめします。不明点がある場合は、必ず葬儀業者に確認しましょう。
葬儀費用を安く抑えるポイントと補助金制度の活用法
葬儀には一定の相場がありますが、工夫次第で負担を減らすことも可能です。ここでは、費用を抑えるための具体的なポイントや、公的制度の活用法について解説します。複数社から見積もり取得
複数の葬儀社から見積もりを取り、費用と内容を比較しましょう。料金が安く見えても、実際には基本プランに含まれていないサービスも多いです。セットプランの内訳やオプションの有無をしっかり確認し、葬儀全体の予算を把握することが大切です。葬儀内容を見直す
葬儀費用は、形式や規模によって大きく変動します。一般葬に比べて、家族葬や一日葬、直葬は参列者の人数も限られるため、会場費や飲食費、返礼品代などを抑えられます。また、料理や葬祭用品もじっくりと検討しましょう。通夜振る舞いや精進落としの料理を、参列者に失礼のない範囲で調整することで無駄な出費を減らせます。さらに、棺や祭壇、生花もグレードに応じて価格が異なるため、必要最低限の仕様に切り替えるのも大事です。
保険やサービスの活用
葬儀保険への加入や各種サービスの利用は、葬儀費用の圧縮に有効なため、検討するとよいでしょう。葬儀保険とは、あらかじめ月々一定額を支払い、死亡時に葬儀費用が給付される保険であり、死亡保険や終活保険と呼ばれることもあります。しかし、申し込みから適用までに時間がかかるため、加入は早めに済ませておきましょう。また、菩提寺がない方には、全国対応の「僧侶手配サービス」も便利です。定額料金で読経などを依頼できるうえ、檀家になる必要もないため、費用を抑えつつ安心して依頼できます。
さらに、生活保護受給者を対象とした、最低限の火葬を公費で支援する制度である「葬祭扶助制度」も、ケースによっては申請できるので利用してみてください。加えて、葬儀社が提供している「互助会制度」と「会員制度」も活用しましょう。
互助会は、将来の冠婚葬祭に備えて毎月一定額を積み立てる制度で、経済産業省の認可を受けた業者のみが運営しています。葬儀費用の一部を充当できるほか、施設利用料の割引や会員優待もあります。
一方の会員制度は、入会金を支払うだけで式場使用料やプランの割引が受けられるというものです。積み立て不要で手軽に始められるため、葬儀を依頼したい業者が決まっている場合には検討しておくとよいでしょう。