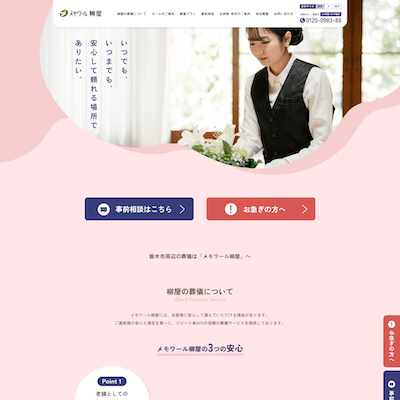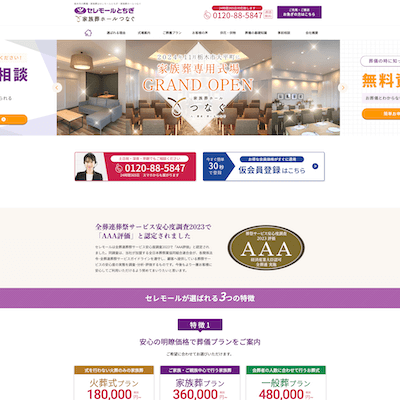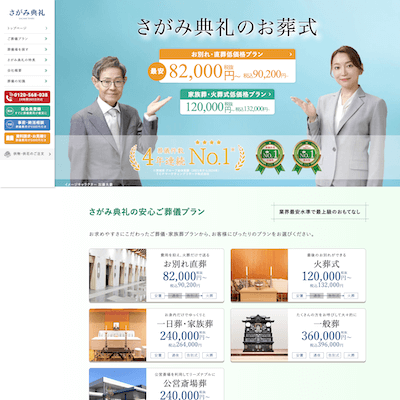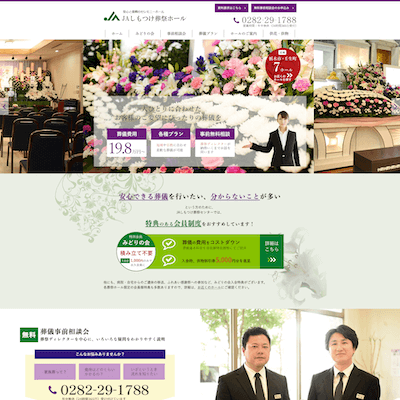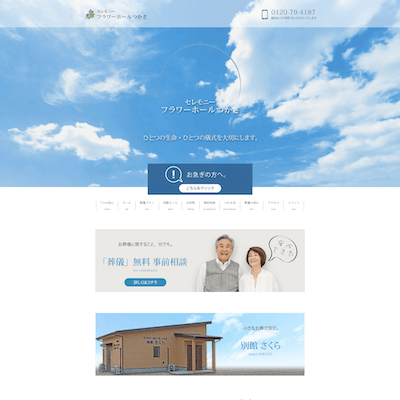家族葬の場合その訃報は、誰に、あるいはどれくらいの関係性の人まで伝えればいいのでしょうか。生前お世話になった人や職場への伝え方やポイントなどをあらかじめ知っておくことで、あわてずに対応することができるでしょう。この記事では家族葬の際の訃報連絡や報告する際のマナーや注意点についても解説します。
家族葬の訃報は誰に伝えるべき?連絡先のポイント
一般的に家族葬は家族や親しい人のみを呼んで行う小規模な葬儀であるため、誰にどのように伝えるかが重要です。基本的には故人の家族、とくに親しかった親族や友人、関係の深い知人など、家族がぜひ知らせておきたいと思う人に絞って連絡するのが基本です。家族葬であることを明確に伝えることで連絡しない相手から不快に思われてしまうなどの誤解を防ぐことができます。また、家族葬でも職場への連絡はしておいたほうがいいでしょう。諸手続きが発生するケースがあるため、会社関係者への連絡は直属の上司や人事担当者に伝えるのがスムーズです。
近隣住民や町内会への連絡は必要に応じて行ってもかまいませんが、参列を辞退してもらう旨をていねいに伝えるのが無難です。
連絡手段として電話やメール、最近ではLINEでもかまいませんが、できるだけ口頭で伝えるのが基本です。故人の意向や生前の交友関係を整理した連絡先リストを作成しておくといいでしょう。
会社や親戚への報告方法と伝える内容
会社や親戚へ報告する際の方法や内容をくわしく解説します。訃報を伝える方法
親族への訃報はできるだけ直接か電話で伝えるのが望ましいです。3親等以内の親族には逝去の際にすぐ一報を入れ、詳細はまた後日伝えるのがいいでしょう。メールやSNSでは伝達が不十分な場合があるため相手の反応を見ながら伝達できる電話が適しています。誰が亡くなったのか
まず最初に伝えるべきは、誰が亡くなったのかという点です。自分との関係を明確に伝えましょう。とくに勤務先へ訃報を伝える際には忌引休暇の取得に関わるため、故人との関係性が重要になります。休暇の日数は会社ごとに規定が異なるため、就業規則などで事前に確認しておくことが大切です。葬儀の形式
家族葬を行う際は家族葬で執り行うことをはっきりと伝える必要があります。葬儀は親族のみで執り行う旨を具体的に説明し、可能であれば電話に加えてメールでも連絡を入れると行き違いを防ぐことができます。大切な人を亡くし混乱している時期ですが、この連絡を怠ると、会社側が参列者を調整し始めたり、香典や供花の準備が勝手に進んでしまうこともあります。何も知らずに葬儀中に職場の方が訪れることもあるため、その際は感謝の気持ちを伝えつつていねいに辞退の意思を示しましょう。
香典をどうするか
香典や弔電、供花・供物を受け取るかどうかは、喪主や遺族の判断によります。家族葬でも職場関係者などから弔問やお供えの申し出があるケースもあり、受け取らない方針であれば、事前にていねいにその旨を伝えておくことが大切です。ただし、会社によっては福利厚生として香典が支給されることもあり、その場合は受け取るのが一般的です。
会社をいつからいつまで休むのか
会社への連絡は、休みの期間を報告することが大切です。詳細まで伝える必要はありませんが、葬儀の日取りだけは伝えておきましょう。忌引休暇がある場合は、故人との関係に応じて取得できる日数が決まっており、続柄を伝えることで確認できます。一般的には喪主を務める一親等のケースでは最長で10日ほど、関係が遠くなると1~2日の休暇がもらえることが多いです。休暇が足りない場合は有給の利用も検討しましょう。
土日をうまく挟めば休暇を短縮できることもあります。復帰を急ぐ必要がある場合は、無理のない範囲で調整を行いましょう。
家族葬の訃報連絡で気をつけたいマナーと注意点
家族葬の訃報連絡をする際に気をつけるべきマナーや注意するべきポイントは次のような点です。できる限り早めに連絡をする
家族が亡くなると遺族は非常に忙しくなり、職場への連絡が後回しになりがちです。しかし、会社側も休暇手続きや業務調整を行う必要があるため、できるだけ早めに連絡を入れることが大切です。タイミングを逃すと社内対応が間に合わず、混乱を招く可能性もあるため、なるべく早めに連絡しましょう。伝えるべき事項をきちんと説明する
家族葬で葬儀の連絡をする際は家族葬で行うこと、参列や香典を辞退する意向があることを明確に伝えましょう。まだ、未定の内容がある場合は決まり次第、できるだけ早めに報告することが望ましいです。業務の引き継ぎを行っておく
突然の訃報により深い悲しみがある中でも職場での業務引き継ぎは忘れずに行いましょう。自分にしか分からない業務内容があると、休暇中に同僚や上司が対応に困ることがあります。電話で伝えきれない場合はメールで詳細を送ると、よりていねいです。業務の進行に支障が出ないよう配慮することが周囲への思いやりです。また、緊急時に備えて連絡が取れる手段や連絡先をあらかじめ伝えておくと安心です。