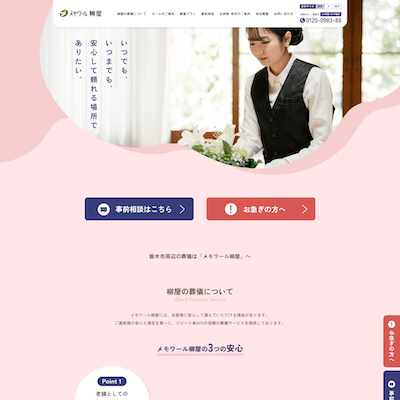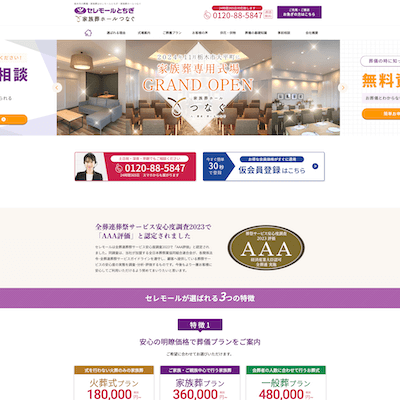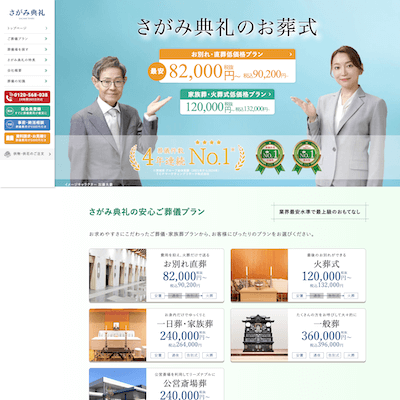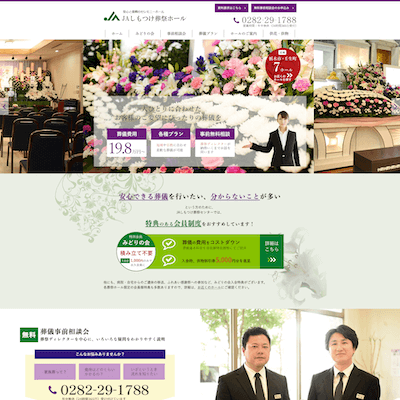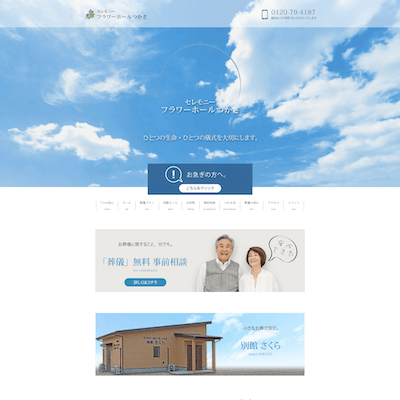大切な家族を失った悲しみの中で葬儀の準備を進めることは、誰にとっても困難な経験です。逝去から火葬まで限られた時間の中で多くの手続きや決定が必要となり、初めて葬儀を執り行う遺族は戸惑うことが多いのが実情です。そこで本記事では、葬儀の一般的な流れと各ステップでのポイントを詳しく解説します。
葬儀の流れと注意すべきポイント
家族が亡くなってから遺体の安置までには、状況に応じた適切な対応が求められます。病院で亡くなった場合は医師による死亡診断書の発行を受け、速やかに葬儀社へ連絡を入れることが必要です。病院の霊安室は数時間以内での移動を求められることが多いため、事前に葬儀社の連絡先を把握しておくことが重要となります。自宅で看取った場合はかかりつけ医への連絡が最優先です。かかりつけ医がいない状況では救急車を呼び、医師の到着まで遺体を動かさないよう注意しましょう。
事故死や突然死の場合は警察への通報が必要となり、検視官による死因特定を待つことになります。訃報の連絡は家族や親族だけでなく、故人の勤務先や友人、菩提寺にも忘れずに行います。とくに菩提寺への連絡は葬儀の日程調整に関わるため早めの対応が大切です。
遺体の搬送先は自宅、斎場の安置室、専用の保管施設から選択できます。自宅安置を希望する場合は布団やドライアイス、枕飾りなどの準備が必要です。葬儀社との打ち合わせでは喪主の決定、葬儀形式の選択、参列者数の予測、予算の設定などを行います。
喪主は故人の配偶者が務めることが一般的ですが、家族構成によっては長男や長女が担当することもあります。死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要がありますが、多くの場合は葬儀社が代行します。
火葬許可証の申請も同時に行われ、この書類は火葬場で必要となるため大切に保管しましょう。葬儀の日程は遺体の状態を考慮し、通常は逝去から3~4日以内に火葬を終えるよう調整します。遠方からの参列者への配慮や火葬場の空き状況、僧侶の都合なども考慮して決定することが求められます。
葬儀・通夜から火葬までの流れと準備すべきこと
納棺は故人との最後の対面となる大切な儀式です。遺族や納棺師によって末期の水を含ませ、湯かんで遺体を清めて死化粧を施し、死装束を着せていきます。棺には故人が愛用していた品物を納めることができますが、金属やガラス製品、貴金属類は火葬の妨げとなるため避けましょう。写真や手紙、花などが一般的な副葬品として選ばれています。通夜は逝去の翌日夜に行われることが多く、開式の2時間前には会場に到着して準備を整えることが大切です。まず受付の設営から始まり、芳名帳や筆記具の確認、供花や供物の配置、席次の確認まで、確認事項は多岐にわたります。
通夜式では僧侶の読経に合わせて喪主から順に焼香を行い、その後一般参列者へと続いていくのが通例となっています。また通夜振る舞いは参列者への感謝の気持ちを表す場となり、軽食や飲み物を用意して接待することが慣例です。
一方、葬儀・告別式は通夜の翌日午前中に執り行われることが一般的となっています。開式1時間前には会場入りし、弔辞・弔電の確認から会葬礼状や返礼品の準備まで、最終確認を行うことが重要です。
式中は通夜と同様に読経と焼香が進められ、閉式後は最後のお別れとして棺を生花で飾っていきます。そして遺族によるくぎ打ちを終えたら、棺を霊柩車に乗せて火葬場へ向かう流れです。火葬には約1時間を要し、その間遺族は控室で静かに待機します。
火葬終了後の骨上げでは、喪主から血縁の深い順に2人1組で箸を使って遺骨を拾い、足の骨から順番に骨壺へ納めていくのが作法となっています。なお、のど仏の骨は最後に喪主が納めるのが一般的です。
火葬場で発行される埋葬許可証は納骨の際に必要となる重要書類のため、紛失しないよう厳重に保管することが欠かせません。もし分骨を希望する場合は事前に申し出て、分骨証明書を取得しておきましょう。さらに火葬から斎場や自宅に戻った際は、塩と水で清めを行ってから建物に入ることが古くからの慣習となっています。
法要・精進落としまでの供養の流れとマナー
火葬後の換骨法要は遺骨を迎えて行う大切な儀式です。自宅や斎場に戻った遺族は塩と水で清められ、僧侶の読経と焼香によって故人の冥福を祈ります。初七日法要は本来逝去から7日目に営むものですが、遠方からの参列者への配慮から葬儀当日に繰り上げて行うことが一般的となっています。地域や宗派によって手順が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。精進落としは、僧侶や葬儀でお世話になった人々を招いて行う会食の場です。かつては四十九日まで肉や魚を断つ精進料理を食べ、忌明けに通常の食事に戻すことを意味していました。
しかし、現在では葬儀が無事に終了したことへの感謝を表す席となっています。喪主は参列者への挨拶で感謝の言葉を述べ、故人の思い出話に花を咲かせながら会食を進めます。席順は僧侶を上座に配置し、遺族は末席に座ることがマナーです。
料理は懐石料理や仕出し弁当が選ばれることが多く、1人あたり3,000円から5,000円程度が相場となっています。お開きの際には僧侶にお布施とお車代を渡し、参列者には引き出物を用意します。精進落としの時間は1時間半から2時間程度が目安です。